①「うまく話すにはTTP」
建設業の現場監督は、朝礼や安全大会にて人前で話す必要があります。経営者であれば、社員さんの前で話さないといけません。しかし多くの方が、話すことがどちらかと言えば苦手で、なんとかうまく話したいと思っています。
私は、現在人前でお話しをする仕事をしていますが、ゼネコンを退社し、起業した当時は、まったくうまく話せませんでした。
そこで毎日のように研修や講演会に出かけ、たくさんの講師の話を聴き、それをまねしようと思いました。そして、あるとき出会った講師の話し方に「ビビビッ」ときました。その講師の話し方をすっかりまねをしようと思ったのです。
TTP(徹底的にパクる)をしたのです。胸に録音機を忍ばせてその方の話を録音し、家で何度も何度も聞きました。そして聞きながら、その声にかぶせて話すのです。その話し方を徹底的に真似て話す練習をしました。
島田紳助・松本竜介という漫才師がいました。
1977年にデビューした後翌年には「上方漫才コンテスト」で優秀敢闘賞を受賞します。
紳助さんは、売れるための漫才を追及するために「笑いの教科書」を作りました。
自分が面白いと思う漫才師の芸をすべてテープに録音し、すべて紙に書き出しました。
そして内容を解体し分析、その違いを比較しました。
たとえば1分間のなかにボケとツッコミのやりとりの「間」がどれだけの数か。
当時「名人」と呼ばれるベテラン漫才師の「間」は20回ほどありました。
これは熟練の技がなせるからで、若手にはマネできません。
「下手でもおもろかったらええ」。
そこで、かれは一人が圧倒的に喋ることで、「間」の足りなさをカバーし、1分間の「間」の数を8個にしてみました。リズムよく喋って間の数を少なくすると、失敗しにくいことに気づいたのです。
当時売れていた海原千里・万里の漫才を分析するとボケのパターンが8割同じだったそうです。100%同じパターンのボケだと、客が飽きてしまいます。だから2割をあえて違うパターンにしていました。野球に例えると、決め球のフォークを8割、ストレートを2割投げているイメージです。ストレートは、あくまで決め球のフォークを目立たせるための見せ球です。
私は人前で話すことは、この「笑いの教科書」と似ていると思うのです。
まずはいいと思うものを分析し、まねをしているうちに、自分のものにしてしまいます。そのうち、独自性がでてきて、光るものが出てくるのです。
次回はさらに詳細にお伝えします。
朝礼でうまく発言するコツ 1 2 3 4
無料ノウハウ集トップページへ戻る
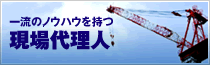 |
現場代理人の育成についてはこちら |
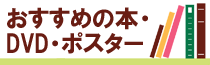 |
【本】『その一言で現場が目覚める』 今すぐ役立つ即効ノウハウ満載!現場リーダー必携の指南書 【DVD】『その一言で現場が目覚める』 現場を目覚めさせるちょっとした一言を実演付き講義で学べます |
