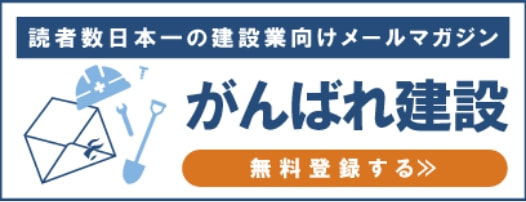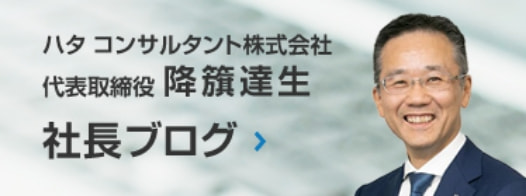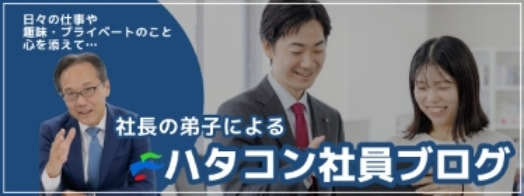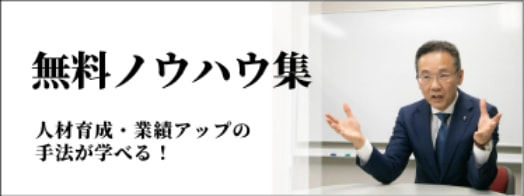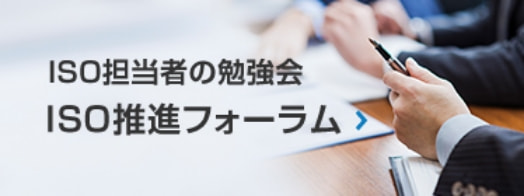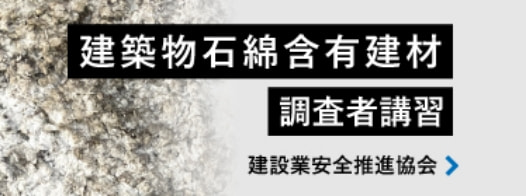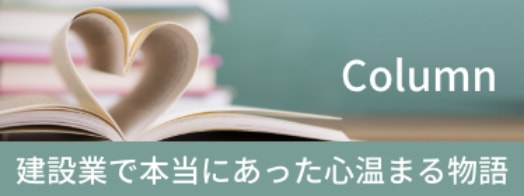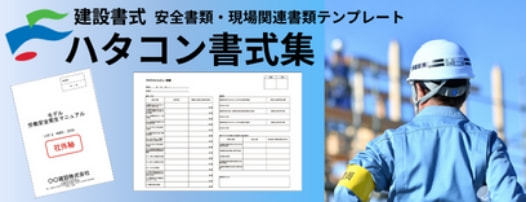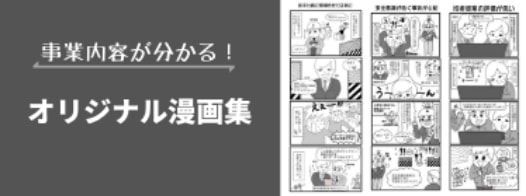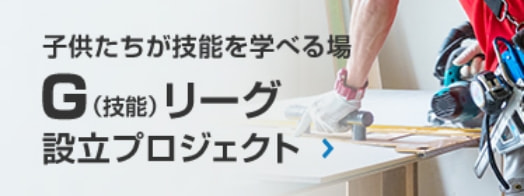■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2025年6月23日
NO2408
◆なぜ「賞与(ボーナス)」制度を曖昧にすると離職者が増えるのか
「賞与は、毎年なんとなく前年踏襲で決めている…」
「評価に差をつけたいけど、基準がなくて決められない…」
このようなお悩みを持つ建設会社の経営者や人事担当の方は多いのではないでしょうか。
賞与(ボーナス)は、定期給与とは異なる一時的な賃金であり、
支給の有無や金額、タイミングも企業の裁量に任されています。
制度設計次第で、従業員のモチベーションを引き出し、
定着率を高めることもできますが、逆に基準が曖昧なままだと
「不公平だ」という不満を招きかねません。
そこで今回は、建設業における賞与制度の見直しに役立つ
基礎知識と設計のポイントをご紹介します。
◆まずは知っておきたい「3つの賞与の種類」
・基本給連動型賞与
「基本給×〇ヶ月分」として支給する方式。
支給月数に評価を反映する場合もあります。
・決算賞与
決算の利益に応じて支給されるもの。いわば利益還元型の特別ボーナスです。
・業績連動型賞与
会社・部門の業績と個人評価をかけ合わせて支給額を決定。
中小企業での導入が進んでいます。
特に最近は、業績連動型賞与を導入する企業が増えており、
従業員の納得感や成長意欲を引き出す仕組みとして注目されています。
◆建設業でよく見られる「賞与の決め方」とは?
以下のような支給方法が建設業でも多く採用されています。
・基本給連動方式:分かりやすく、規模の大きな会社に向いています。
・等級・役職別定額方式:中小企業で導入しやすい一方で、
納得感に課題が残る場合があります。
・支給基準×個人評価方式:柔軟性があり、公平感も得やすい仕組みです。
・利益分配方式:業績と連動しやすく、柔軟に賞与総額を調整可能です。
◆「業績連動型賞与」の設計3ステップ
ステップ1:業績指標の設定
営業利益、当期純利益など、自社の長期的な目標と合致する指標を選びましょう。
個人の業績評価をする場合は、1人あたり限界利益を採用するのが良いと思います。
ステップ2:賞与原資の算定
経営計画に基づくシミュレーション、過去実績に基づく分析など、
根拠をもって設定することが重要です。
ステップ3:個人評価の係数を設定
5段階評価(例:A=1.5、B=1.3…)を基に、相対評価の仕組みを
取り入れる企業が増えています。
◆賞与制度を運用する上での注意点
ルールの明確化と周知
曖昧な制度は不信感につながります。指標や基準を開示しましょう。
減額時の説明責任
業績や評価によるものであれば、正当性を伝える必要があります。
制度改定時の混乱回避
複雑な制度設計は避け、シンプルでわかりやすく。
従業員からのフィードバックも忘れずに。
退職者・産休者への対応
賞与支給の可否や社会保険料の取り扱いにも要注意です。
◆賞与制度も「技術提案」と考えよ
施工現場では、品質・コスト・工期のバランスを考えながら、
常に最適解を探っていきます。
同様に、賞与制度も「働きがい」や「評価の納得感」という視点から、
技術提案的に改善していく必要があります。
「制度設計に正解はない」とはいえ、試行錯誤しながら改善する姿勢が、
会社への信頼と人材の定着を生むのです。
若手技術者のやる気を引き出すには「適切な評価と正当な報酬」が欠かせません。
このタイミングで、賞与制度の見直しを検討されることをお勧めします。
私が共著で執筆した書籍「『建設会社の賃金管理』
~これだけは知っておきたい!~」
では、建設業に合った賃金制度と評価制度を解説しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/4492261222←こちらをクリック
社長ブログ