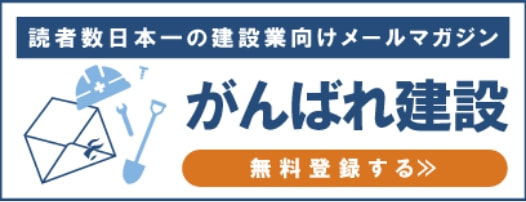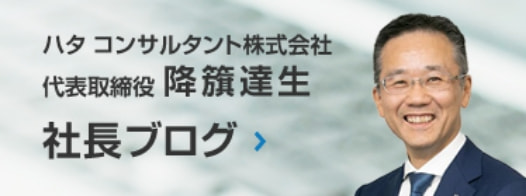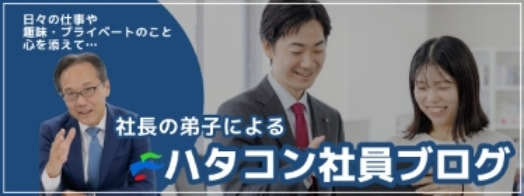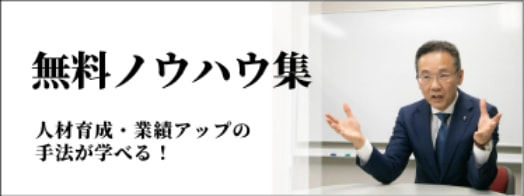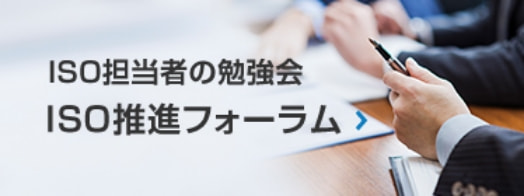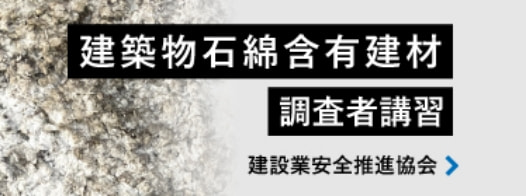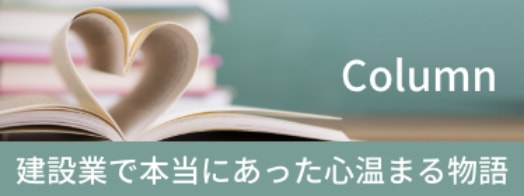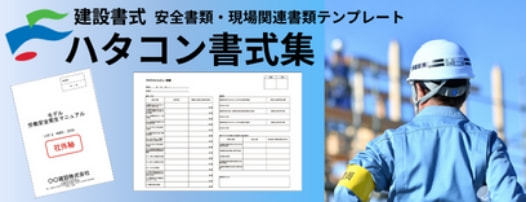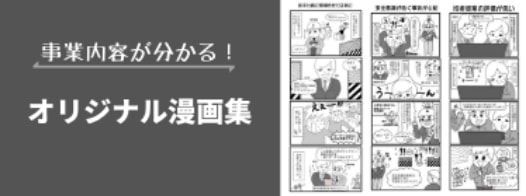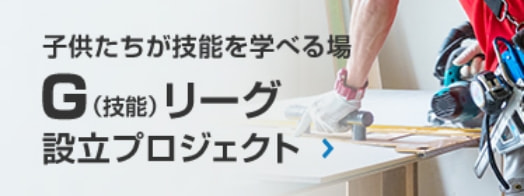■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2025年8月4日
NO2424
◆なぜ上司は若手社員の向上心を奪ってしまうのか
最近読んだ記事の中で、
キングス・カレッジ・ロンドンの認知科学者
ガイ・クラクストン氏の言葉が印象的でした。
「消しゴムは『間違いは恥』の文化を作る。
実社会では間違いは起きるのだから、
間違いを受け入れた方がいい。」
海外ではボールペンを使わせる
小学校も多いそうです。
子供がどこで間違えたかのプロセスを
見ることが大切だからです。
これは建設現場の若手技術者育成にも
通じる話だと思います。
◇現場でありがちな「ゼロリスク思考」
建設業界でも「失敗=恥」という
空気が強いと感じることがあります。
小さなミスでも総叩きに遭い、責任を恐れて
新しい工法やICT導入を避けてしまう。
結果として「無難な選択しかしない現場」になり
若手の主体性や成長の芽を摘んでしまいます。
しかし現場の技術者は、
変化や新しい挑戦に取り組まなければ
成長できません。
失敗を避けるために守りに入ると、次第に
「自分で考える力」が弱まってしまうのです。
その結果、向上心を失ってしまうのです。
◇アントレプレナーシップを持つ
東京学芸大学大学院の小宮山利恵子氏は、
失敗を許すための考え方として
「アントレプレナーシップ教育」を
挙げています。
具体的には以下の5つの力です。
気づく力:新しい視点で現場を見直す力
対話する力:協力会社や仲間と共創する力
探究する力:好奇心を持って学び続ける力
行動する力:考えを実行に移す力
失敗する力:挫折を成長の糧に変える力
この中でも最後の
「失敗する力」が特に重要です。
若手が安心して挑戦できる環境を作ることが、
現場の活性化や生産性向上にもつながります。
◇現場でできる工夫
・失敗を共有する場を作る
月次会議で「成功事例」だけでなく
「失敗事例」も発表する。
失敗を責めるのではなく、
再発防止策や学びをみんなで考える。
・大失敗大賞をつくる
挑戦したが失敗した若手を表彰する
建設会社もあります。
「チャレンジを称える」文化づくりは
士気を高めます。
・上司が「笑って許す」という一言を意識する
部下がミスをしたとき
「大丈夫だ、次に活かそう」と
声をかけるだけで雰囲気は変わります。
若手社員に向上心がないと感じるのは、
若手社員の責任ではなく、
上司に失敗を許す勇気がないことが原因です。
◆まとめ
建設現場は安全第一が大前提です。
しかし安全・品質を確保した上での
「挑戦の余地」をつくることが、
若手育成にも会社の未来にも不可欠です。
失敗を笑って許し、
学びに変える現場をつくりましょう。
それが「ゼロリスク思考」から抜け出し、
イノベーションを生む第一歩です。
*************************************************
【編集後記】
*************************************************
先週末に次期の経営計画会議を開催しました。
建設業界のお役立ち企業となれるよう
新たな商品開発をします。
*************************************************
社長ブログ