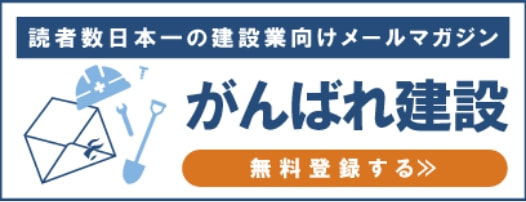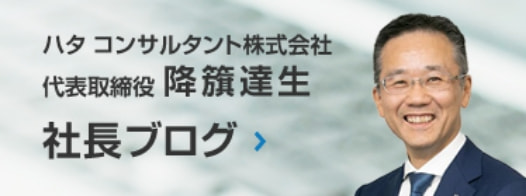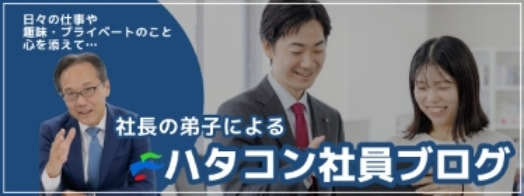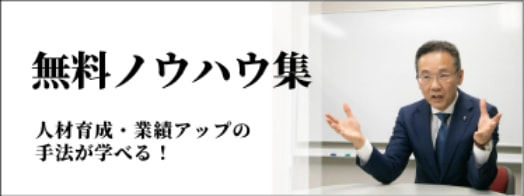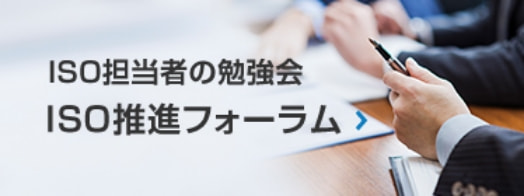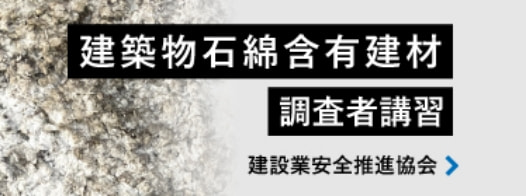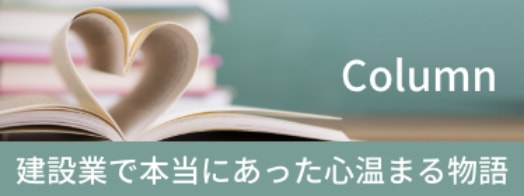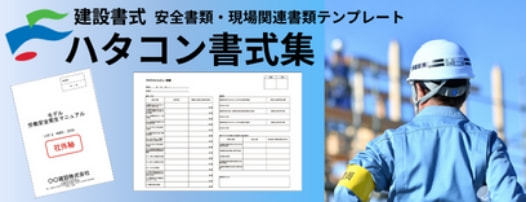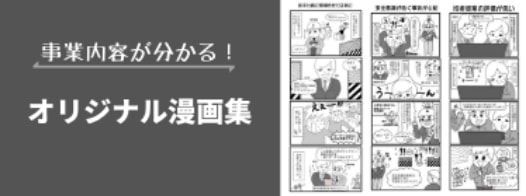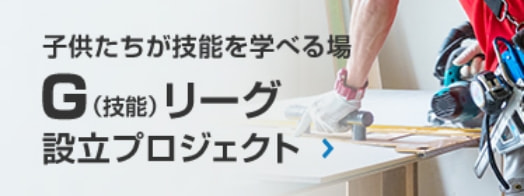■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2025年10月1日
NO2446
◆なぜ今、建設業界に「主体的人材」が求められるのか
建設業界では、若手の育成や人材不足が
大きな課題となっています。
その中で今、注目されているのが
「主体性の高い人材」の育成です。
「主体性」は、他者からの指示を待たず、
自らの意志で考え、
積極的に行動する姿勢を指します。
そのため、「主体的人材」は、
まさに「自主的に動き、自らの判断で仕事を
進められる人材」を表す言葉と言えます。
では、どうすれば現場で
そのような人材が育つのでしょうか。
今回は、主体的人材が育つ組織に共通する
「3つの特徴」をご紹介します。
◆1.経験学習の仕組みがある
現場では毎日、さまざまな出来事が起こります。
しかし、ただ経験するだけでは
成長にはつながりません。
**経験を振り返り、学びに変える「仕組み」**
が必要です。
たとえば、
・朝礼や夕礼で「今日の気づき」を共有する
・週1回の1on1面談で行動目標を振り返る
・工事完了後に「良かった点」「改善点」をチームでまとめる
このように、「やって終わり」ではなく
「やったことを振り返り、次につなげる」場が
あることで、現場での経験がスキルとして
積み上がっていきます。
◆2.挑戦を受け入れる風土がある
ある現場では、若手社員が
新しいICTツールの導入を提案しました。
しかし上司の「前例がないからダメだ」の
ひと言で却下されてしまいました――
これは非常にもったいない話です。
挑戦が歓迎され、失敗しても評価される
風土こそが、主体的人材を育てます。
たとえば、
・新しい工法を提案してきた若手に「おもしろな」と受け入れてみる
・新しい工法を試した若手に「よくやった」と声をかける
・失敗したとしても、チャレンジした行動そのものを評価する
挑戦の余地がある現場には、
やる気と創意工夫が生まれます。
◆3.心理的安全性と学びの文化がある
「こんなことを言ったら怒られるかも…」
「自分でやってみたいけど、失敗したら責任取らされそうだ」
そんな気持ちが蔓延している現場では、
人は自律的に動けません。
主体的人材が育つ現場には、
「心理的安全性」があります。
つまり、「自分らしく発言し、失敗しても
受け入れてもらえる安心感」です。
さらに、学ぶ文化が根づいていることも重要です。
・書籍購入やセミナー受講の費用補助がある
・先輩が読んだ本を若手に紹介する
・勉強会や外部講師を招いた研修が開かれている
こうした環境が整っている組織では、
若手も自然と「もっと学ぼう」と
思うようになります。
◆まとめ:若手の自律は「仕組み」と「文化」で育つ
主体的人材は、
「気合い」や「根性」だけでは育ちません。
必要なのは、経験を学びに変える仕組み、
挑戦を評価する風土、安心して学べる文化です。
どれも今すぐ取り組める内容です。
まずは自分の現場で、
「どれが足りていないか?」を
振り返ってみてください。
成長とは、行動の数ではなく、
振り返りの質で決まる。
振り返りと学びの場をつくることが、
組織を育て、人を育てます。
*************************************************
【編集後記】
*************************************************
本日、ハタ コンサルタント株式会社は
27期となりました。
新たな経営計画書をもとに、
より建設業の発展に資するよう取り組みます。
*************************************************
社長ブログ