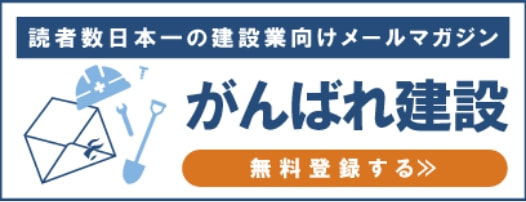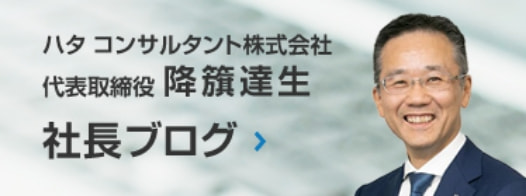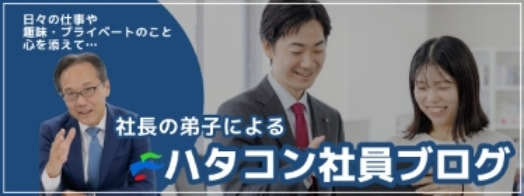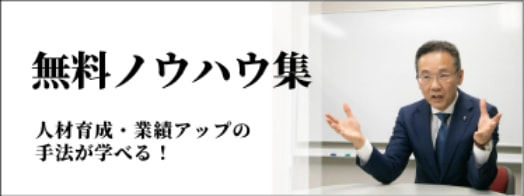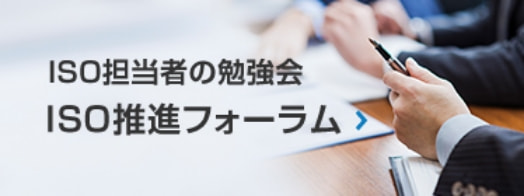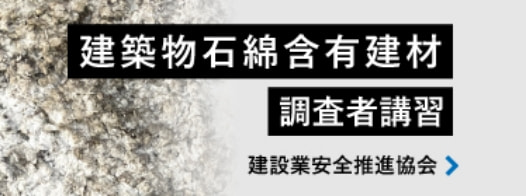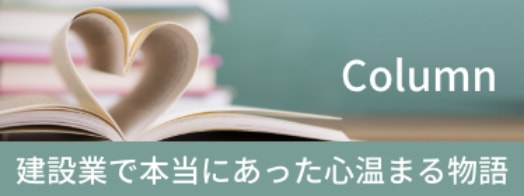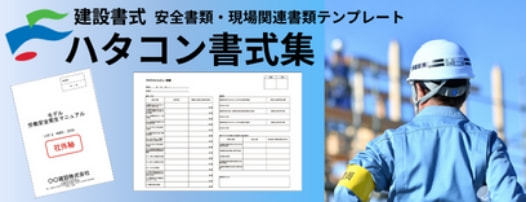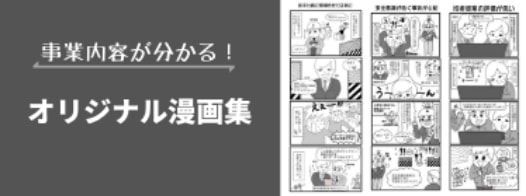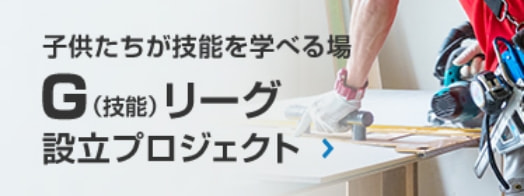■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2025年9月1日
NO2434
◆現場で必要な書式を無料提供
契約、届出、品質、工程、安全、ISO等建設工事現場で
使用する書式(Excel版 記載事例付き)を無料でダウンロードできる
「ハタコン書式」サイトを開設しています。
現場業務の生産性向上に役立ちます。
https://www.hata-web.com/safety-documents/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=202509format ←こちらをクリック
なお、219書式を一括ダウンロードできるCDを
以下より入手できます(有料)。
https://www.hata-web.com/safety-documents/ ←こちらをクリック
◆なぜ現場トップは「いつも上機嫌」でいなければならないのか
朝の通勤電車で舌打ちをする人、
挨拶を無視して通り過ぎる人、
少しのことで店員に怒鳴る人…。
齋藤孝氏の著書
『不機嫌は罪である(角川新書)』には、
現代人がいかに「慢性的な不機嫌」を抱えて
生きているかが描かれています。
この「不機嫌」は、自分だけでなく、
周囲の人にも悪影響を与えます。
建設現場においても同様で、
所長や代理人といった現場のトップが
不機嫌な態度で現れると、
現場全体の雰囲気は一気に悪くなり、
作業員のやる気や安全意識にも影響を及ぼします。
SBIホールディングスの北尾吉孝会長は、
「トップは常に発光体でなくてはならない」
と語っています。
つまり、現場のトップは、曇った空気の中でも、
太陽のように明るく振る舞う必要があるのです。
それでも、
「そんな簡単に機嫌よくなんてできませんよ」
と思われるかもしれません。
実際、工程の遅れやクレームなど、
日々のストレスは尽きません。
しかし、重要なのは
「自分の機嫌は自分で取る」という意識です。
SNSで誰かを攻撃したり、
部下に八つ当たりしたりしても、
事態は何も変わりません。
むしろ周囲の人たちが萎縮し、
現場の活力が失われていきます。
齋藤氏はこう言います。
「不機嫌でいることは甘えである。
相手を選んで不機嫌になるのは、
自分の立場を利用した攻撃である」と。
つまり、叱られても反撃しない
立場の弱い部下に対して怒りをぶつけるのは、
指導ではなく単なる支配です。
建設業の現場はチームで成り立っています。
そのチームの長が、
無意味な不機嫌をまき散らしていたら、
チームの士気が下がり、安全・品質・工程、
すべてに影響が及びかねません。
上機嫌でいることは、
部下のモチベーションにも直結します。
以前のメルマガでも紹介しましたが、
脳科学的にも「プラスの言葉」や「笑顔」は、
周囲の脳にポジティブな刺激を与え、
やる気を引き出す効果があるのです。
建設現場のトップとして、
以下のことを意識してみてはいかがでしょうか。
【現場トップの「上機嫌」を保つ5つの習慣】
1)朝の「おはよう」に笑顔を添える
2)自分の気分を上げるルーティンを持つ(お気に入りの本や音楽など)
3)部下や協力会社の「よいところ」を1日1つ見つけて声に出す
4)怒りそうになったら「深呼吸」してから話す
5)不機嫌な人には近づかず、「上機嫌な人」と付き合う
私自身も、過去には現場で
イライラしてしまうことがありました。
しかし、そのときにふと思い出したのが、
ある施主からいただいた
「ありがとう」という手紙でした。
それを見返すことで、自分の気持ちが
スーッと落ち着いたのを覚えています。
上機嫌は努力で保つもの。
誰かに求めるのではなく、
自分自身でつくるものです。
ぜひ、現場の空気を変える
「上機嫌の技術者」を目指していきましょう。
*************************************************
【編集後記】
*************************************************
話題になっている映画「国宝」を観てきました。
とてもよい映画でしたが、
書籍「国宝」はさらによいです。
とりわけ文章が
まるで映画を観ているような表現なのです。
大きな舞台で震える役者の様子
「毎日舞台が終わりますと、
まっすぐ自宅に帰り、まるで背骨を抜くように
体を休め、また朝になれば、動かぬ体に
むち打って劇場に来るのが精一杯・・・」
怒り狂う暴力団組長
「今にもこぼれそうなその眼球に
血を滲ませ「あんた何もんや?」」
私自身、映画を観ているような
メルマガを書きたいと思いました。
(日本講演新聞8/4を一部参考にしました)
*************************************************
社長ブログ