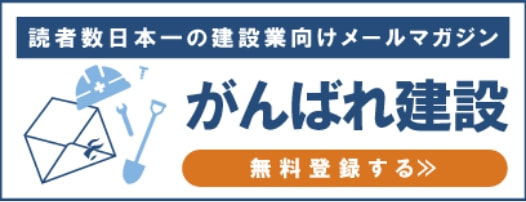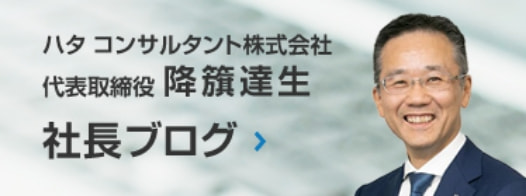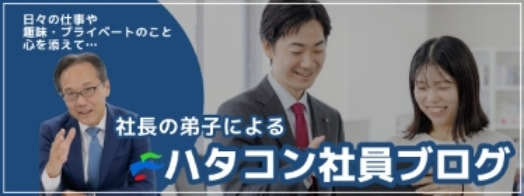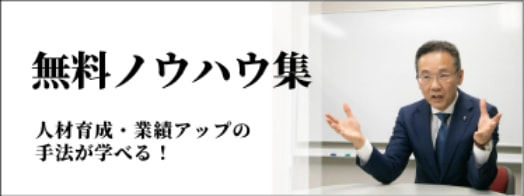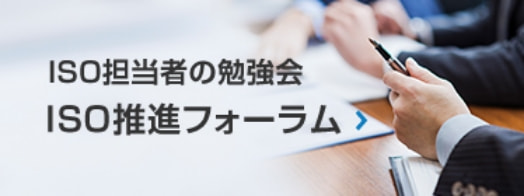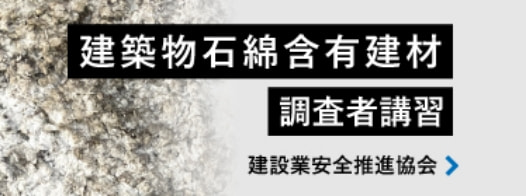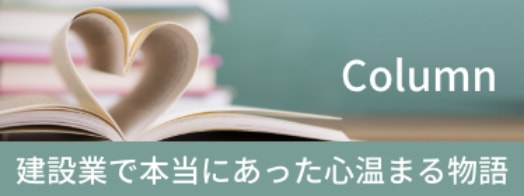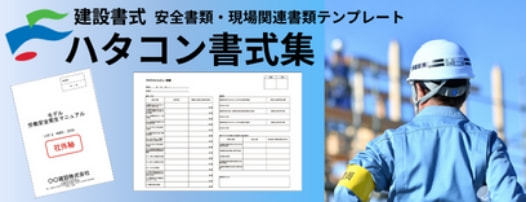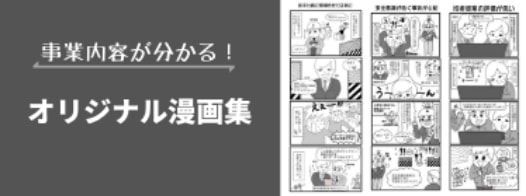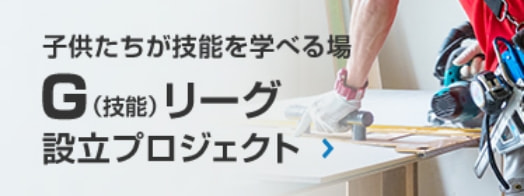■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2025年10月24日
NO2455
◆“内定者研修”が現場での活躍を左右する─新人教育は入社前から始まっている
来春に向けて、そろそろ内定者研修の設計が
本格化している時期ではないでしょうか。
「何を教えるべきか」「どこまで踏み込むか」
「現場とどうつなげるか」──
研修の方向性に悩んでおられる
担当者の方も多いかもしれません。
特に建設業界では、
現場配属後のギャップに苦しむ
若手技術者が少なくありません。
その原因の多くは
「入社前後の育成設計のズレ」にあります。
◆内定者研修でよくある“つまずきポイント”
以下は、建設業界でもよく見られる
新人研修の悩みです。
・内容が座学中心で、現場との接点がない
・ 担当者によって教え方・指導の温度差が大きい
・ インプットが多く、アウトプットの場が不足
・ 実務とのギャップが大きく、現場で戸惑う
・ 人手不足で、教育に十分な時間が割けない
特に若手技術者からは、
「聞いていた話と現場が違った」
「何をすればいいのか分からなかった」
という声が多く上がります。
◆新人が“現場で動ける人材”になる5ステップ
現場につながる新人教育を設計するには、
次の5つのステップが有効です。
1)現状把握
まずは、アンケートやオンライン面談で
内定者のマインドとスキルを把握しましょう。
「建設業に対する理解度」や「PCスキル」
「コミュニケーション力」などの可視化が第一歩です。
2)ゴール設計
「配属までに、何ができるようになっていてほしいか?」
を具体的な業務レベルで明示しましょう。
例:「KY活動での発言ができる」
「簡単な安全書類が読める」など。
3)ロードマップ提示
到達ゴールに向けたステップを、
本人と共有することが重要です。
やらされ感を減らし、納得感を持って
研修に取り組めるようになります。
4)カリキュラム編成
座学だけでなく、
「現場見学」「ケーススタディ」
「簡易プレゼン」などを組み合わせましょう。
配属後のリアルな状況を想定した
アウトプットの場を必ず設けてください。
5)配属後フォロー
現場配属後は、OJTだけに頼らず、
1on1面談やeラーニングを活用して
継続的なフォローを行いましょう。
「つまずきポイント」を早期に察知することが、
離職防止にもつながります。
◆「学び直し」ではなく「つながる学び」を
最近では、内定者研修と入社後研修が
断絶しているケースも見受けられます。
・入社後にゼロから教え直す
・内定者研修での学びが活かされていない
これでは、研修にかけた時間もお金も
“もったいない”使い方です。
学びを“点”で終わらせず、
“線”につなげることが、
これからの育成には欠かせません。
◆結びに──「入社前の設計」が現場の生産性を決める
若手技術者が現場で活躍するには、
「現場の技術」と同じくらい
「組織としての準備」が必要です。
内定者研修は、
配属後の生産性を左右する“投資”です。
「誰が教えるか」「何を教えるか」
「どう現場にバトンを渡すか」を、
今一度見直してみてはいかがでしょうか。
ハタ コンサルタント株式会社では
「【オンライン】初めて建設業で働く人のための建設業入門セミナー」
を開講しています。
多くの内定者や、中途採用者が参加されています。
【現場の安全】
2025年11月17日(月)13:00 - 17:00
【図面の読み方】
2025年12月15日(月)13:00 - 17:00
【建設業の基礎】
2026年1月19日(月)
【現場コミュニケーション】
2026年2月16日(月)
詳しくはこちらです。
https://hata-web.com/open-seminar/3724/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=202510Introduction ←こちらをクリック
2026年4月入社される新入社員研修は、
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、
広島、福岡、オンラインにて開講します。
詳しくはこちらです。
https://x.gd/mC6XN?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=202510shinnyuusyain ←こちらをクリック
*************************************************
【編集後記】
*************************************************
ハタコンでは、経営計画発表会にて、
前期の充実体験を発表します。
充実体験がたくさんありすぎて悩みながら、
何を話そうかを考えています。
*************************************************
社長ブログ