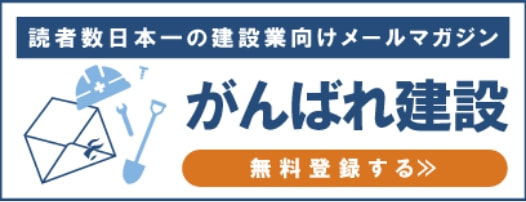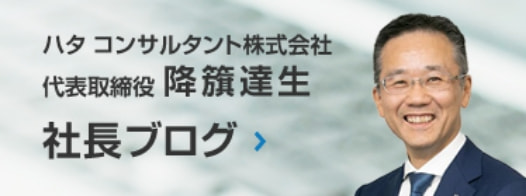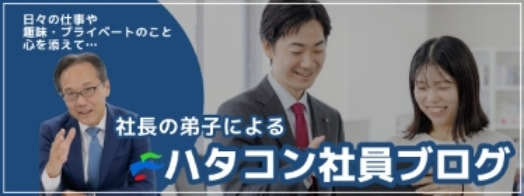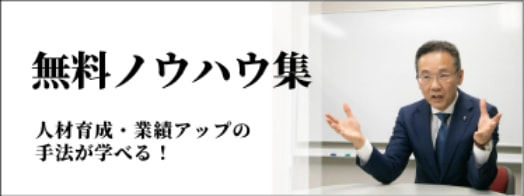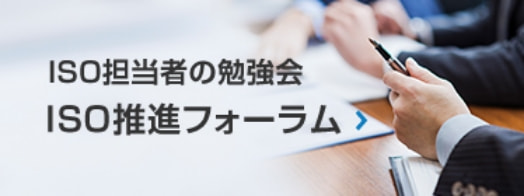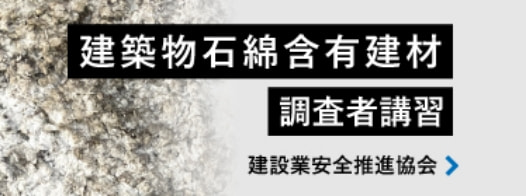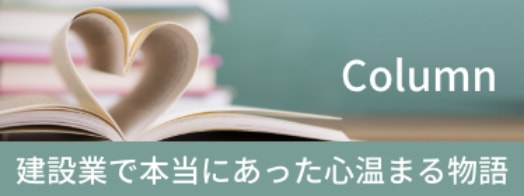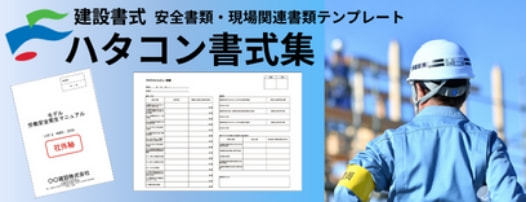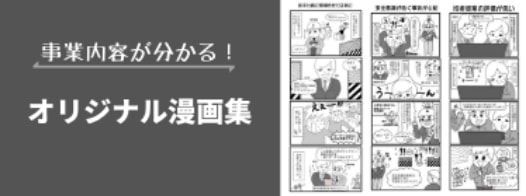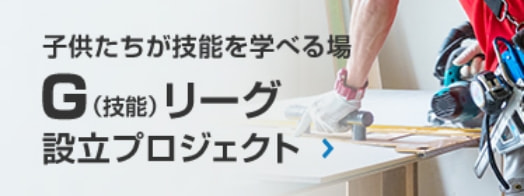■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2025年8月18日
NO2428
◆現場でのイライラや焦りの気持ちを受け流すにはどうすればよいのか
建設現場は常に変化とトラブルの連続です。
工程の遅れ、急な仕様変更、
近隣からのクレーム、職人同士のトラブル…。
こうした出来事が重なると、
イライラや焦りで冷静さを失い、
判断ミスや人間関係の悪化を招くことも
少なくありません。
そんな時に役立つのが、禅の教えである
「二念を継がない」という考え方です。
泰丘良玄氏(泰岳寺副住職)はこの言葉を
「受け流す練習」と表現しています。
現場で感情に振り回されないためのヒントとして
ぜひ取り入れてみてください。
■「二念を継がない」とは
「二念を継がない」とは、
嫌な出来事や不快な出来事が起きた時、
最初に湧き上がる感情(一念)は
否定せずに受け止めるが、
そこから次の思考(二念)につなげない、
ということです。
例えば、ある職人さんから
厳しい言葉を投げかけられたとします。
一念:「嫌だな」「腹が立つな」
二念:「言い返してやろうか」
「あの人はいつもこうだ、嫌な人間だ」
この二念を積み重ねていくと、
怒りや不安が増幅し、
感情の奴隷になってしまいます。
冷静さを失えば、現場の雰囲気も悪くなり、
最終的には品質や安全にも悪影響を及ぼします。
■現場でよくある「二念」の例
工程が遅れているとき
一念:「遅れているな、どうしよう」
二念:「あの協力会社のせいだ」「このままでは終わらない、最悪だ」
発注者から厳しい指摘を受けたとき
一念:「きついな、悔しい」
二念:「あの人は自分のことを信用していない」「今後も無理難題を言われるに違いない」
若手がミスをしたとき
一念:「またか、困ったな」
二念:「あの子は成長しない」「自分ばかり苦労している」
一念までは自然な感情です。
しかし、そこから二念を重ねると、
怒りや不安がどんどん膨らみ、
物事を正しく見られなくなります。
■「二念を継がない」ための実践法
〇一念を認める
怒りや不安を抑え込もうとせず、
「今、自分はカチンときているな」と認識する。
他人事のように自分の感情を観察するイメージです。
〇次の思考につなげない
「なぜこんなことになった」「誰のせいだ」
と考えるのは後回し。
感情が落ち着いたら、
冷静に事実を整理すれば十分です。
〇呼吸に意識を向ける
イライラした時は深呼吸を2~3回。
呼吸に集中することで
感情のスイッチを切り替えやすくなります。
〇「今やるべきこと」にフォーカスする
過去や未来の不安にとらわれず、
目の前の作業に集中する。
これだけでも余計な二念を抑えられます。
■リーダーほど「二念を継がない」意識が大切
現場をまとめる立場の人ほど、
冷静さが求められます。
上司や協力会社、発注者との板挟みになる場面も
多く、感情的になりやすい立場だからです。
・ミスやトラブルが起きても、事実だけを見て判断する
・部下や協力会社を感情的に責めない
・自分の感情を一旦受け止めてから行動する
この姿勢が現場の雰囲気を安定させ、
チーム全体のパフォーマンス向上につながります。
■「二念を継がない」を習慣化するために
禅の世界では「一念は湧き上がるままに、
二念を足さない」という修行を続けると、
やがて一念そのものも少なくなり、
無心に近づくといわれます。
もちろん、
いきなり無心になることはできません。
しかし、毎日の中で
「二念を継がない」練習を少しずつ続けると、
驚くほど気持ちが楽になります。
・クレーム対応中に深呼吸を一つ
・誰かの言葉にカチンときたら「一念まで」とつぶやく
・就寝前に「今日は二念を継がずに過ごせたか」を振り返る
こうした小さな習慣が、
現場の安定と自分自身の成長につながります。
■まとめ
・「二念を継がない」とは、一念(最初の感情)
の後に余計な思考を重ねないこと
・二念を継がないことで、感情に振り回されず冷静な判断ができる
・特に現場をまとめる立場の人ほど、意識的に取り入れることが大切
建設現場では日々、大小さまざまな
トラブルや想定外の出来事が起こります。
そのたびに二念を重ねていたら、
心が疲れ切ってしまいます。
「二念を継がない」という禅の教えを
現場で実践し、冷静で安定した
リーダーシップを発揮していきましょう。
*************************************************
【編集後記】
*************************************************
今日から仕事という方が多いかもしれませんね。
身体がなまっている可能性があるので、
くれぐれもご安全に。
*************************************************
社長ブログ