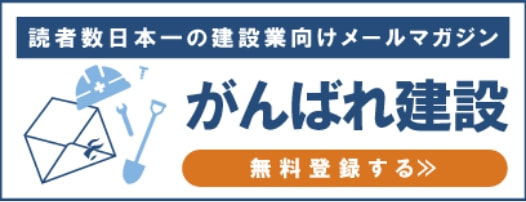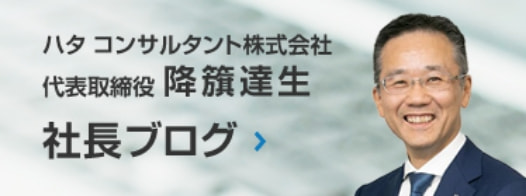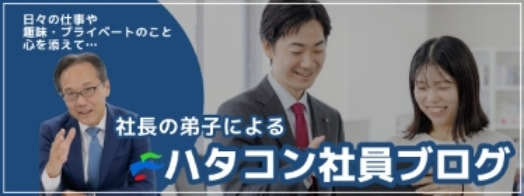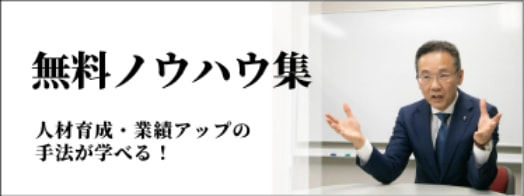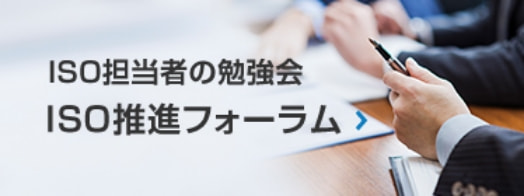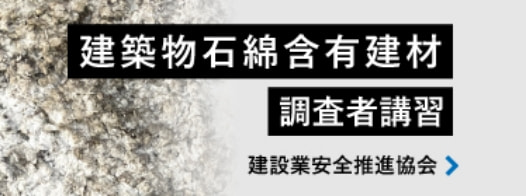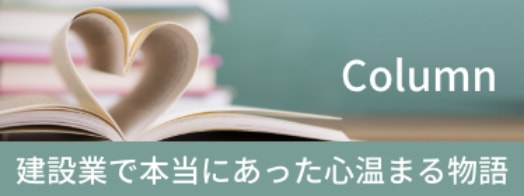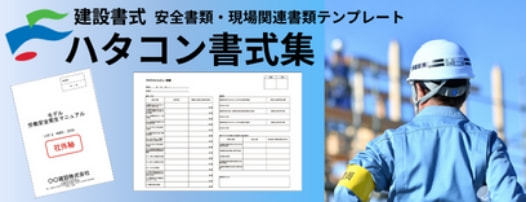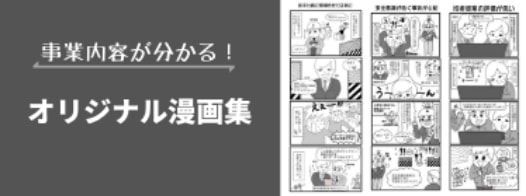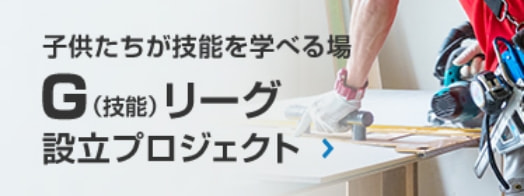御社のご紹介をお願いいたします
滋賀県に本社を構える和晃は、空調・換気設備、給排水・衛生を行う会社です。
滋賀県は災害が少なく、水資源が豊富で、交通の便が良いことから大手企業の工場が多数集まるエリアです。
和晃は、そうした地元の経済を担う企業の生産ラインを維持するためのエンジニア集団です。
また、生産ラインの付帯設備工事のみならず、電気・建築・土木工事の専門協力会社と連携することにより、
ワンストップでの対応を可能とし、顧客の様々な要望に応え続けています。
その他、店舗や住宅の空調・衛生設備から上下水道に至るまで、様々な事業を展開しています。

一 人を大切にする会社「和晃」 一
経営理念は「人」。
社員とその家族。協力会社、取引先、そしてお客様。
当社に関わるすべての「人」の幸せの実現をめざしています。
人と人の繋がりがあってこそ成り立つ仕事。人を繋ぎ、そして未来へと繋いでいきます。

Hatacon Movie を導入した部門・部署を教えて下さい
今回、動画研修を導入したのは、現場の第一線で活躍する技術職を中心とした部署です。
具体的には、以下の職種の社員が対象となっています。
・現場施工管理技術者
・配管技能工
・技術営業スタッフ
・事務員
現場での業務に直結する知識から、お客様対応や社内業務の効率化に役立つ内容まで、
幅広い学びを提供することを目的としています。
技術職に限らず、事務スタッフも含めた全員が対象となることで、
部門全体としてのスキルの底上げと、共通認識の醸成にもつながっています。

Hatacon Movieを導入いただいた経緯と、その際にお持ちだった課題についてお聞かせください
Hatacon Movie導入のきっかけは、幅広い職種に対応した学習カリキュラムが整っており、
誰でも手軽に学べる環境を整えられる点に魅力を感じたからです。
また、e-ラーニングに慣れることができる点や、導入コストの安さも決め手となりました。
導入前は、集合型研修を開催する際に日程や場所の調整が難しく、
学習の機会を継続的に設けることが課題となっていました。
さらに、DVDなどの教材を複数用意するにはコストがかかり、オンライン講習やe-ラーニングに不慣れなため、
知識の吸収が思うように進まないことも懸念材料でした。
こうした背景から、柔軟な学習スタイルを実現し、学びの定着につなげる手段として、
Hatacon Movieの導入を決定しました。
Hatacon Movie導入に際して、苦労したことは何かございましたか?
導入そのものに大きな障壁はありませんでしたが、
最初の段階では「なぜ導入するのか」「どのような目的があるのか」といった点について、
社員一人ひとりに理解と納得を得ることに少し時間を要しました。
特に、初めてe-ラーニングに触れる社員も多く、
従来の学習スタイルとは異なる新しい取り組みに対して、
戸惑いの声が一部であがる場面もありました。
そこで、導入の背景や目的を丁寧に説明し、
どのようなメリットがあるのかを具体的に伝えることで、徐々に社内の理解と協力が進みました。
今では、「自分のペースで学べるのがありがたい」「繰り返し視聴できるので理解が深まる」といった
前向きな声も増えており、着実に浸透してきています。

Hatacon Movie導入後の変化・効果についてお聞かせください
Hatacon Movieを導入してから、最も大きな変化は「空き時間を使った短時間学習の習慣化」です。
業務の合間やちょっとした空き時間に、社員が自発的に動画を活用するようになりました。
導入から8か月が経過した時点での学習時間は、社員1人あたり 月最大5.8時間、最低でも0時間 という実績が出ており、
業務状況に応じて柔軟に学習機会を確保できていることが分かります。
また、学んだ内容を社員同士で共有する場面が増えたことで、
部署を超えたコミュニケーションが活性化された点も、
嬉しい副次的効果のひとつです。
「知識を学ぶだけでなく、話題にもなる」
そんな学習文化が少しずつ根づき始めていることを実感しています。

今後の展開や予定をお聞かせください
今後は、Hatacon Movieの活用をさらに定着させるために、
学習の実施状況を継続的に管理しながら、
社員一人ひとりの学習状況に応じたサポートを行っていく予定です。
具体的には、まだ学習が習慣化していない社員に対して、
個別のフォローやアドバイスを行うことで、
より自発的に学べる環境づくりを進めていきます。
動画学習を単なるツールにとどめず、
「学ぶ文化」を根づかせていくことを目指しています。

Hatacon Movieの利用1年後に、継続をされた理由をお聞かせください
Hatacon Movieを継続的に活用しているのには、いくつかの理由があります。
まず、新入社員や若手社員に対して、動画視聴による学習を日常的な習慣として根づかせたいと考えているためです。
短時間でも継続して学ぶ環境を整えることで、知識の定着と成長スピードの向上を期待しています。
また、インターンシップのプログラムの一環としても動画コンテンツを活用しており、
学生にも自社の業務や安全管理への理解を深めてもらうツールとして役立っています。
さらに、日常業務ではなかなか学ぶ機会が限られていたベテラン社員にも視聴を促しており、
キャリアに関係なく継続的に学べる環境づくりに貢献しています。
若手からベテランまで幅広い層が対象となることで、組織全体の底上げにもつながっていると感じています。
最後に、定期的なコンテンツの更新や、新たな動画配信への期待があります。
いわば、YouTubeのように新しい情報が次々と追加されることで、
「次はどんな内容が見られるのか」という前向きな関心が生まれ、社員の継続的な視聴につながっています。
常に最新の知識や現場で役立つ情報に触れられることで、日々の学びが自然と習慣化されていく、
そんな環境づくりに大きく貢献していると感じています。